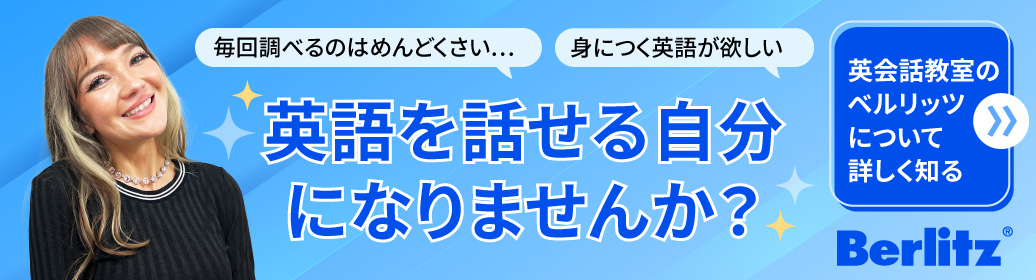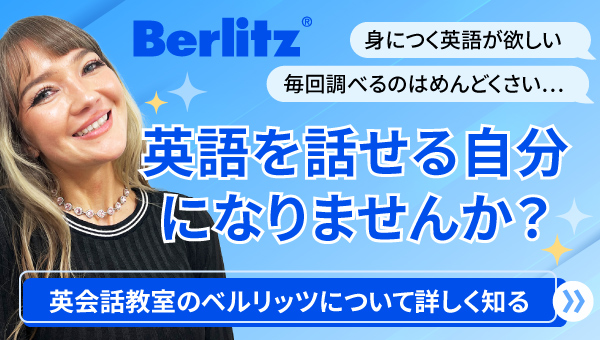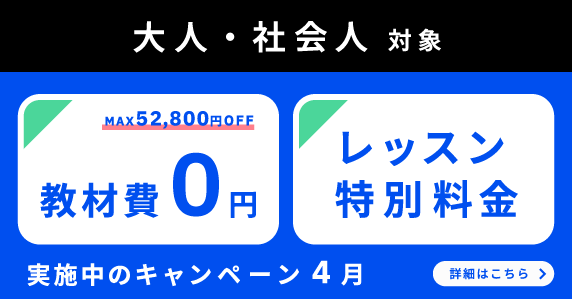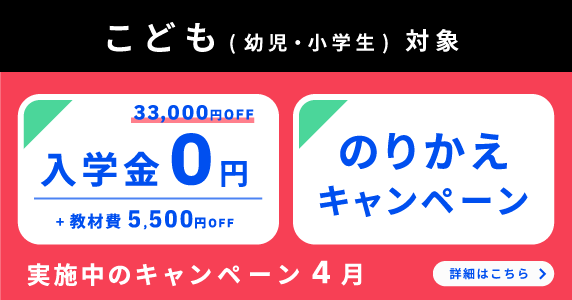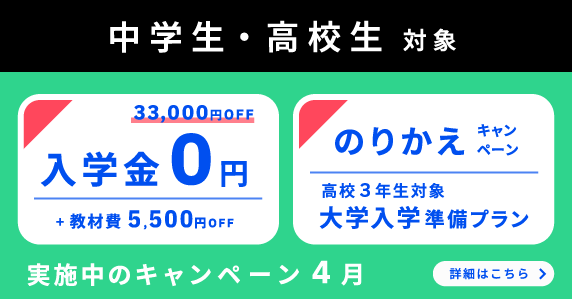1-2-2. 仕事においての好奇心とモチベーション
ビジネスの場面で好奇心によって生み出されるモチベーションの代表的な例として、自ら施策を考えるケースを取り上げます。
施策を考え、実行する時に行う次の4つのことは、前述の旅行でモチベーションが生み出される状況と似ています。
① 旅行先で目にしたいことを思い浮かべ、ネットやガイドブックで調べる ≈ 問題や状況を分析する
② どんな場所・物かイメージし期待を抱く ≈ 仮説を立て、施策を考える
③ 実際に目の当たりにする ≈ 施策を実行する
④ 期待を裏切られたり、凌駕されたりする ≈ 結果が出る
10代の女子学生に人気のあるファッション雑誌を制作している出版社があるとします。
読者目線では市場で一定の地位を確立しているものの、広告主離れという問題を抱えているとします。
「雑誌の売上部数からして読者からは人気のある雑誌であることは明白なのに、広告掲載を控える企業がいるのはなぜなのか?」
と疑問に思っている新任編集長Aさんの話を例にして、好奇心からモチベーションが生まれる仕組みを、順を追って見てみましょう。
① 問題や状況を分析する
Aさんはまず、これまでの広告主に出稿を見送った理由を尋ねてみようと考えました。
数社に問い合わせたところ、多くの担当者が「費用対効果が安定しない」ことを理由として述べました。
費用対効果が低いというのならいざ知らず、安定しないとはどういうことなのでしょう?
②仮説を立て、施策を考える
Aさんは、化粧品やファッション関係の商品の広告掲載後、10代の女子学生の購買につながる時とつながらない時があることから、以下の可能性を考えました。
仮説A: 広告自体の質がまちまち
仮説B.: 10代女子学生が大半である読者のお小遣い事情が関連している
これらの仮説の真意を確かめたいと思い、回答者に特典をプレゼントをする形で、Aさんは読者アンケートを行うことにしました。
③施策を実行する
Aさんは別件で制作し在庫が余っていたノベルティーグッズを特典として、抽選で200名に当たるプレゼント付きの読者アンケートを作成しました。
アンケート内容は以下の通りです。

もし仮説Aが正しければ、投票がほとんど入らない広告があるはずです。
もし仮説Bが正しければ、「月によって異なる」にたくさん投票が入るはずです。
早く結果が見たいという思いと共に、アンケート集計の日を待ちます。
④結果が出る
アンケートの結果、以下のことがわかりました。
■ アンケート回答者は売上部数の50%に上った。特典欲しさで回答してくれたにしても、熱心な読者が大勢いることが確認できた。
■ 問1に関しては、投票が入った広告はほぼ均等に分かれた。どの広告も好意的にとられていたことが確認できた。
■ 問2に関しては、「月によって異なる」が圧倒的に多かった。これにより、女子中学生や高校生は月々定額のお小遣いをもらっていたとしても、使途がファッション以外に多様で、月々にファッションに使える額が安定していないことが判明した。
結果的に仮説Aは間違っていたようです。対して仮説Bは予想通りでした。
熱心な読者が多いにも関わらず広告の費用対効果が安定しないのは、そもそもターゲット層の消費の使途が(おそらく友達付き合いなどの理由で)一定ではないからです。
そこで、Aさんは大胆な策を思い付きます。「今確保している熱心な読者の成長と共に、雑誌のターゲット年齢層を上げていくのはどうか」と。
読者がアルバイトを始めたり就職したりして自らお金を稼ぐようになるにつれ、お金がより大事なものに代わり、使途の多様性は軽減されていくでしょう。
時間はかかるものの、成長した読者をターゲットにすれば、広告の効果も安定していくのではないか、と考えました。
この施策の成否を確認したいという好奇心が、Aさんを再び突き動かしていきます。
Aさんのように自ら考えた施策が効果的であるかどうか、またどうすれば改善できるのかを考える時、好奇心を素にしたモチベーションが生まれます。
さらに、施策が成功した時に、今まで効果があるかどうかわからなかったことが、効果があるということがわかります。
つまり、「なかった」知識が「ある」状態に変わり、達成感を得られ、モチベーションに変わります。
仕事にクイズ要素を見出すことで、仕事の中で好奇心が満たされるようにすると良いでしょう。