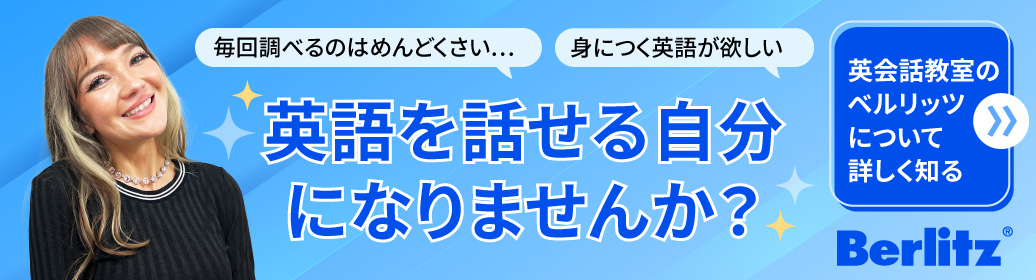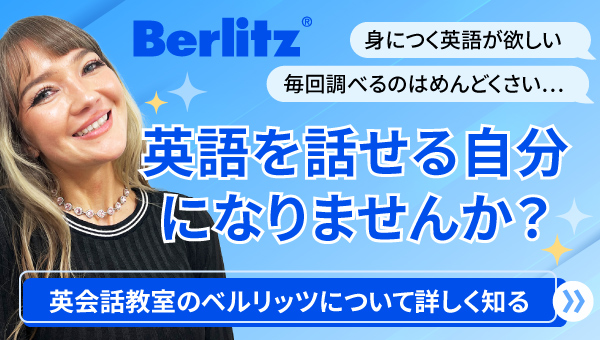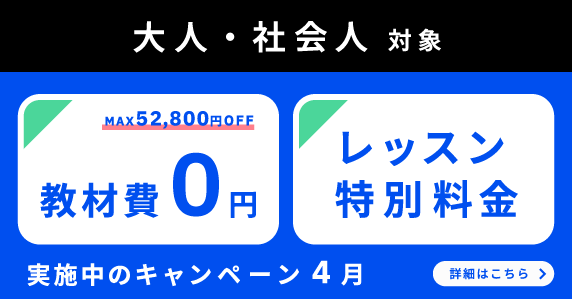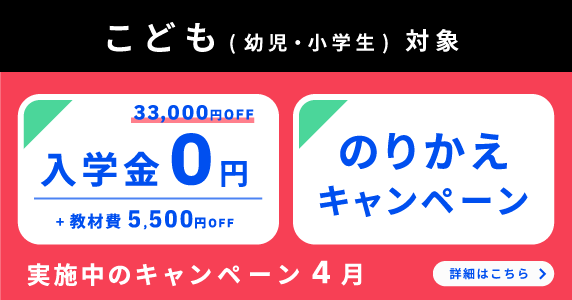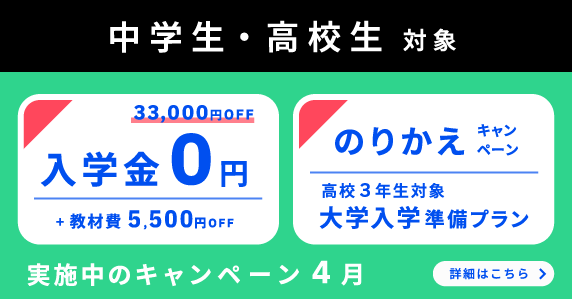人材育成における他流試合とは:分野・業界の異なる者同士が議論や問題解決などに取り組む研修やワークショップといった能力開発の場
他流試合が昨今注目され始めているのはなぜなのでしょう?
ウェブやアプリ事業参入のハードルが劇的に下がった今、ありとあらゆる分野のビジネスパーソンたちが自分たちのアイディアとITを融合させ、イノベーションを次々と起こしています。
この現象は分野の垣根を越えて協働したりアイディアを掛け合わせたりすることで、単一的な組織には成し得ない画期的な商品やサービスを生みだすことができることをわかりやすい形で表しています。
多様性を取り入れ上手くマネジメントできる組織は、強いのです。
だからといって、自らの組織の社員構成を今日からガラッと変えるなどそうそうできることではありません。
とはいえ、自分たちだけでは考えつくことができないようなアイディアはやはり欲しい。
多くの企業が感じているはずのジレンマです。
このような問題に対して即効性のある解決策が、他流試合です。
自らの組織の社員を入れ替えるなど大掛かりなことをすることなく、新しい風を取り入れることができる方法です。
今回は他流試合が組織と人材に施す恩恵についてお話しします。