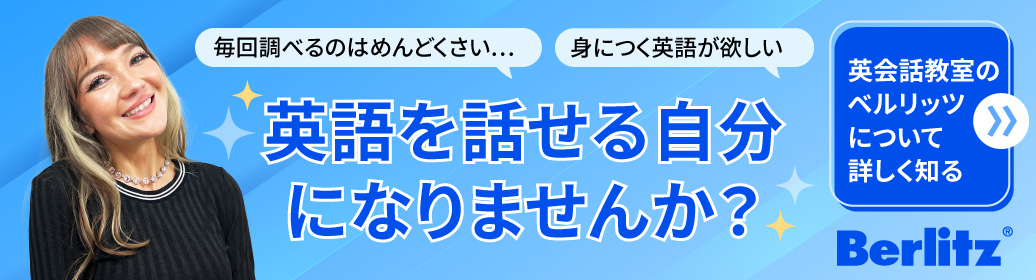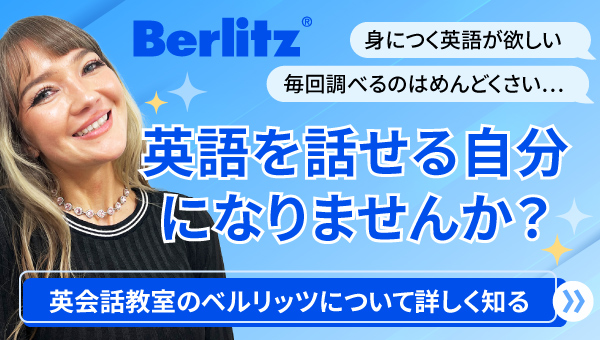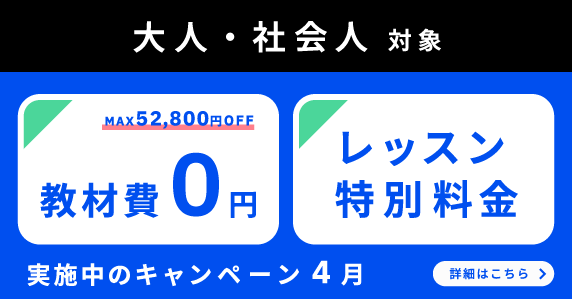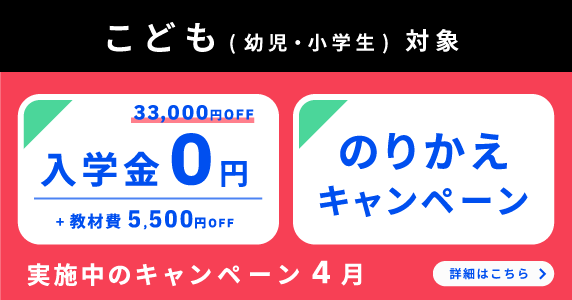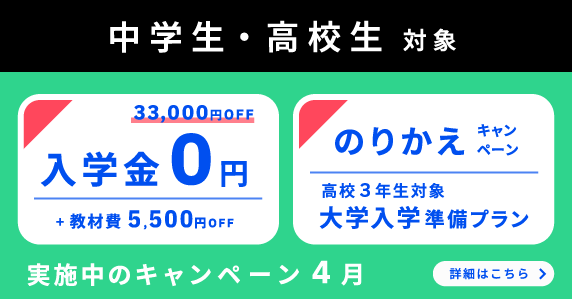2-1. 見切り発車が伴うリスクがわかるシチュエーション
以下のシチュエーションを想像してみてください。
背景
アメリカはワシントンD.C.にある大口の新規顧客に数回に渡って訪問し、先方が自社の商品購入を真剣に検討してくれていて、次の会議で契約を締結できる見込みであるとします。
先方企業の経営者は教育を重んじるユダヤ教の信者であることもあり、とても博識な人物です。多くのユダヤ人社員を束ねています。
あなたは一か月前の8月に行われた最後の会議では仕事の話に留まらず、様々な話題を話す中で、先方との親睦を深められた手ごたえを感じています。
見切り発車が判明
この勢いのまま契約を締結させたいと思い、9月下旬に再び渡米するための飛行機・ホテルの手配、先方へのメールなどを、チームや上司と確認することなく、よかれと思い自分一人で一気に済ませてしまいました。
後日、先方の返信が珍しく遅いなと思っていたところに、上司が声をかけてきました。
「D.Cのお客様との次の会議をそろそろ設定した方がいいな。9月は難しいだろうから10月の後半くらいで打診してみたらどうだ。」
「え?なんで9月が難しいんですか?9月中に契約できるように今資料を用意していますよ。それに一昨日メールで、前回からちょうど一か月後の9月15日あたりで契約日をご提案しておきました。」
「なんで先に確認しなかったんだ。知らなかったんだろうけど、ユダヤ教は9月のどこかが新年祭の祝日だよ。すぐに調べなさい。」
調べた結果、今年は9月13日の夕方から9月15日までがユダヤ教のローシュ・ハッシャーナーという新年祭の期間であることがわかりました。
宗教上の決まりで、この期間中は一切働いてはいけないのだそうです。
「日本の正月三が日にお客様に伺わせてください、と言っているようなものだ。
すぐに電話して謝りなさい。知らなかったとはいえ大変失礼なことだ。」
コンセンサスを得ずに行動した後の周りの評価
先方は、
「異文化どうしの取引にはありがちなことです。お気になさらないでください。ですが次回の会議は10月にお願いします。」
と寛容な対応をしてくれたものの、上司からのあなたの評価は以下の通りになります:
大変熱意とスピード感溢れる人材だが、失敗が会社全体にもたらす影響を軽く見積もっていて、慎重さに欠いている。
まだ大きな仕事を任せるわけにはいかないな。
また、チームメンバーからの評価は以下になります:
今回は先方が寛容だったから大事に至らなかったものの、今後、せっかくみんなで積み上げた成果を台無しにしかねない。